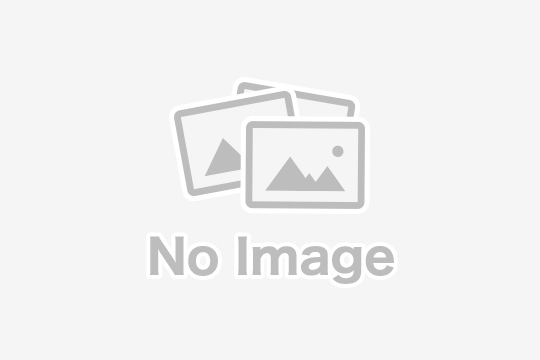この記事は約 5 分で読めます。
こんにちは、めしラボです。
鉄フライパンの洗い方には「洗ってはいけない」「洗剤を使ってはいけない(または洗剤を使ってきれいに洗った方が良い)」「金たわしを使ってはいけない(または金たわしを使った方が良い)」など様々な情報が入り乱れています。
個人的には竹ササラを使って水(またはお湯)だけで洗うことをおすすめしています。
 めしラボ
めしラボ今回の記事は次のような人におすすめ!
- 鉄フライパンの洗い方の理屈を知りたい。
- 「汚らしくなる」「くっつきやすくなる」などの問題に悩んでいる。
- 通常の洗い方とリセットのような洗い方の違いを知りたい。
鉄フライパンは特有の洗い方があります。
おすすめは竹ササラ(もしくは柄のついたブラシなど)を使って汚れをかき出すように洗うことです。竹ササラとは竹を束ねてブラシ状にした道具です。一般的には中華鍋を洗うために使われることの多い道具ですが、鉄フライパンを洗うためにも便利です。
熱を持ったフライパンでもガシガシ洗えますので汚れが残りにくくなります。
スポンサーリンク
鉄フライパンの洗い方は?
鉄フライパンはフッ素樹脂加工のフライパン以上に念入りに洗います。
フッ素樹脂加工のフライパンは表面加工(フッ素樹脂加工)があるために洗い残しがあっても大きな問題にはなりませんが、鉄フライパンの表面には酸化被膜(四酸化三鉄)と油膜の層しかありませんので汚れにより腐食が生じてしまうことがあります。
そのため鉄フライパンの洗い残しは厳禁です。
鉄フライパンが熱を持っているうちに少量の水を加えて汚れを浮かせます。多少の焦げ付き程度であれば熱と水分により簡単に落とせるようになります。あまりにも焦げ付きがひどい場合にはそのまま火にかけて(煮立たせて)汚れを浮かせるようにします。
step.1
竹ササラや柄のついたブラシなどを使って汚れをかき出します。洗剤を使わなくても問題はありませんが油汚れが気になる場合には食器洗い洗剤や重曹を使うこともあります。金たわしに関しては油膜を剥がしてしまうことからも積極的にはおすすめしません。
step.2
洗い終えたら火にかけて水分を飛ばします。火にかけることにより油が浮いてきてしまうこともありますが、キッチンペーパーなどで拭き取っておけば問題はありません。ノンスティック加工の施されていない鉄フライパンには異種金属接触腐食(ガルバニック腐食)などのリスクがありますので重ねないで収納しておくことをおすすめします。
step.3
以上が基本的な鉄フライパンの洗い方です。
しかし絶対的な正解はありません。プロの料理人であっても「洗剤を使わずに洗うこと」を推奨している人もいれば「定期的に洗剤や金たわしで洗うこと」を推奨している人もいます。これは料理の種類や使用頻度によっても変わってくる問題です。
まずは試してみることをおすすめします。
鉄フライパンは失敗してしまっても何度でもリセットすることが可能ですので、自分のスタイルに合った方法を模索していく必要があります。個人的には「通常は竹ササラを使って洗い、汚らしくなってきたタイミングで洗剤や重曹を使って洗う」ようにしています。
いずれにしても「洗い残しを作らない」ことが大切です。
汚れ残りが鉄を腐食させる?
汚れ残りは鉄をさびさせます。
鉄フライパンに焦げ付きなどの汚れを残してしまうと金属表面に電位差の異なるアノードとカソードが生じます。この電位差により鉄(Fe)がイオン化(Fe2+)することで腐食が進行して水酸化第一鉄(Fe(OH)2)が生成されます。
水酸化第一鉄はさらに酸化することにより水酸化第二鉄(2Fe(OH)3)や酸化第二鉄(Fe2O3)になります。
鉄フライパンや中華鍋などを使い続けているとうっかり汚れを残してしまうこともあるかと思いますが、後日汚れを落としてみると油膜や酸化被膜が剥離されて金属面がむき出しになっているのを目にしたことのある方も少なくはないはずです。
それこそが汚れにより鉄が腐食してしまった痕跡です。
多少の腐食であれば腐食個所の油膜や酸化皮膜が剥がれる程度で済みますが、そのまま腐食を進行させてしまうと(特に板厚の薄い中華鍋などにおいては)鍋底に穴が開いてしまうこともありますので注意が必要です。
鉄フライパンは洗剤を使わずに洗いますが、汚れ残りは厳禁です。
鉄フライパンへの重曹の利用法は?
鉄フライパンは重曹を使って洗うことがあります。
鉄フライパンの汚れは油が酸化したものです。たとえば鉄フライパンの内側に意図的に作られる油膜は油が酸化重合したものですし、外側にこびり付く汚れは酸化重合により粘度の高くなった油に埃や水垢などが混じり合ったものです。
そこで弱アルカリ性で研磨力のある重曹を使います。
重曹(炭酸水素ナトリウム)には「弱アルカリ性であるために油汚れを中和して落としやすくする」「研磨作用があるために油汚れに対して物理的に作用する」などのメリットがあります。そのため鉄フライパンの頑固な油汚れにもおすすめできます。
鉄フライパンでの重曹の使い方には大きく2パターンがあります。
| 重曹水にして使用する | 拭き掃除やつけ置き洗浄用として |
|---|---|
| 重曹ペーストにして使用する | 研磨剤(クレンザー)の代わりとして |
難しく考える必要はありません。
たとえば鉄フライパンが全体的に汚らしくなっている時には重曹水で煮ることによりこびり付いていた油汚れが落ちやすくなりますし、鉄フライパンの外側などのように部分的な油汚れを除去したい場合には重曹ペーストをつけて丸めたラップやアルミホイルでこすることで簡単に落とせるようになります。
また重曹は50~60℃に加熱すると洗浄力が向上します。
まとめ・鉄フライパンの洗い方は?
鉄フライパンは洗い残しがないように念入りに洗います。
調理後の鉄フライパンは、熱を持っているうちに少量の水を加えて竹ササラ(もしくは柄のついたブラシなど)を使って汚れをかき出すようにして洗います。多少の焦げ付き程度であればこの方法できれいに洗い流すことができます。
あまりにもひどい汚れには「水(または重曹水など)を煮立たせる」「重曹ペーストと丸めたラップやアルミホイルでこすり洗いをする」こともありますが、通常の管理には水と竹ササラがあれば大丈夫です。
おすすめの関連アイテム
厚板フライパン 極(リバーライト)
- 材質:
- 鉄(特殊熱処理)
- 板厚:
- 3.2mm
- 重量:
- 0.83kg
リバーライトの厚板タイプです。
特殊熱処理(窒化処理)が施されていることに加え「3.2mmの厚板仕様になっている(通常タイプは1.6mm)」「木製のハンドルが採用されている」などの特徴があります。これにより「耐摩耗性や耐食性に優れる」「酸化皮膜を形成させる必要がない」「熱容量が高いことにより料理の仕上がりが良くなる」「ハンドルが熱くならない」などのメリットが得られます。
管理人のレビュー
特殊熱加工が施されていることに加え「一般家庭の台所においても違和感のないデザイン」が気になっています。現在使用している鉄フライパンはデバイヤーですが、機会があれば使いたい(切り替えたい)と考えています。
IH対応鉄フライパン(デバイヤー)
- 材質:
- 鉄
- 板厚:
- 2.5mm
- 重量:
- 1.38kg
デバイヤーの定番鉄フライパンです。
盛り付けをしやすいハンドル角度とデザインの良さが魅力の鉄フライパンです。高品質な厚板の鉄が使われていることもあり、安価な鉄フライパンと比べると格段に使いやすい(食材がくっつきにくくサビにくい)仕様になっています。
管理人のレビュー
デザインの良さが気に入って使っています。しかしデバイヤーの特徴ともいえるハンドル角度には「蓋が干渉してしまう」というデメリットもあります。お使いの蓋の流用を考えている場合には注意が必要です。
打出し 鉄 フライパン(山田工業所)
- 材質:
- 鉄(打ち出し)
- 板厚:
- 2.3mm
- 重量:
- 1.25kg
山田工業所の定番フライパンです。
通常の鉄フライパンはプレス(圧力を加えて成型する方法)などで作られていますが、山田工業所の鉄フライパンは打ち出し(たたいて成形する方法)で作られています。これにより鉄の分子が詰まり、硬く粘りのある性質を持つようになります。
管理人のレビュー
機能性を重視するのであれば山田工業所の打出し鉄フライパン一択かと思います。事実、多くの飲食店では山田工業所の鉄フライパンや中華鍋が好まれています。デザインが好みで台所の印象と合うのであれば心からおすすめできます。
竹ささら(遠藤商事)
- 材質:
- 竹
- 長さ:
- 235mm
- 重量:
- 105g
中華鍋に用いられることの多い竹ブラシです。
家庭での鉄フライパンの洗浄には少し長めに感じられるかもしれませんが、熱を持ったまま洗うことの多い鉄フライパンの洗浄では少し長めくらいの方が使いやすいです。気兼ねなく使える価格帯であることからもおすすめできます。
管理人のレビュー
一般的な竹ささらです。そのままでは硬く洗いにくいことからも「10分ほど煮る」「束ねられている部分に瞬間接着剤をしみ込ませる」「先端を剪定鋏などで斜めにカットする」などをして扱いやすくすることをおすすめします。
フライパン洗い ブラシ(マーナ)
- 材質:
- 馬毛
- 長さ:
- 25cm
- 重量:
- 80g
柔らかい馬毛のブラシです。
馬毛は耐熱・耐薬品性に優れているため、表面を傷つけることなく優しく洗い上げることができます。鉄フライパンを洗うには心もとなく感じられるかもしれませんが、ある程度育っているフライパンに洗剤を付けて洗う場合にはおすすめできます。
管理人のレビュー
鉄フライパンの扱いに慣れていない場合には竹ささらをおすすめします。しかしほとんど焦げ付かせることがなく育ってきた油膜を傷つけないように洗いたい場合などには重宝します。ある程度の油慣れをしているフライパンであれば洗剤で洗っても問題ありません。
超強力マグネットフック(Sendida)
- 材質:
- ステンレス鋼
- 耐荷重(垂直方向):
- 10kg
- 耐荷重(水平方向):
- 7kg
強力なマグネットフックです。
フック部分の回転する強力マグネットフックですので、溝やつなぎ目の少ないタイプのレンジフードでも鉄フライパンなどを吊るす(かける)ことができます。耐荷重は「垂直方向10kg」「水平方向7kg」ですので厚板の鉄フライパンであっても安心です。
管理人のレビュー
レンジフードには溝のあるタイプ(ブーツ型)と溝のないタイプ(スリム型)の2種類があります。ブーツ型の場合は溝に掛けるタイプのフックを使えますが、スリム型の場合には超強力なマグネットタイプのフックがおすすめです。