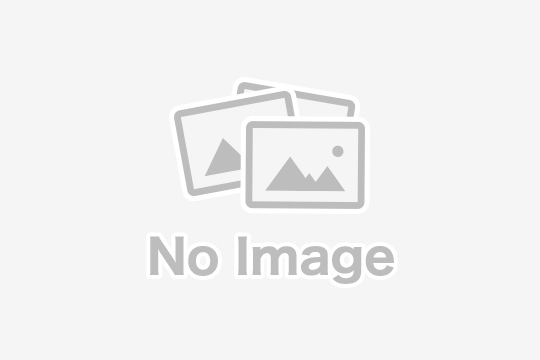この記事は約 5 分で読めます。
こんにちは、めしラボです。
鉄フライパンは優れた調理道具ですが、フッ素樹脂加工(テフロン加工など)のフライパンに慣れ過ぎていると「食材がくっついて使いづらい」「洗っただけなのにサビてしまう」などの不満から使わなくなってしまうことがあります。
しかし鉄フライパンは何度でもやり直しがききますので、気が向いた時でもリセットしてやり直してみると面白いかと思います。もちろん日常的に使用している鉄フライパンを(汚れの除去などを理由に)リセットすることもあります。
鉄フライパンは愛着のわきやすい調理道具です。
 めしラボ
めしラボ今回の記事は次のような人におすすめ!
- 鉄フライパンのリセット方法は?
- 頑固な焦げ付き汚れの落とし方は?
- 使っていなかったフライパンの再生方法は?
鉄フライパンは何度でもリセットできます。
たとえば「使っていなかった鉄フライパンがサビていた」「油汚れや焦げ付き汚れが蓄積して汚らしくなってしまった」「焦げグセがついてしまって使いにくい」などの場合にはリセット(サビ、油汚れ、焦げ付き汚れの除去など)をすることにより再生させることができます。
鉄フライパンを扱う上では覚えておきたいテクニックです。
スポンサーリンク
鉄フライパンのリセット方法について
鉄フライパンのリセット方法には大きく2パターンがあります。
それが「物理的なリセット方法(空焼きをして油汚れや赤サビを焼き切る方法)」と「化学的なリセット方法(アルカリ性洗剤や酸性洗剤を使うことで油汚れを除去する方法)」です。これにより新品の時のような使い心地になります。
どちらの方法にも一長一短があります。
- 物理的なリセット方法:高温に熱することで油汚れなどを炭化させる方法
- 化学的なリセット方法:アルカリ性洗剤と酸性洗剤を使い分ける方法
おすすめは物理的なリセット方法です。
物理的なリセット方法は油汚れを燃やして(炭化させて)落とします。油汚れは炭化させることで簡単に落とせる(ポロポロと落ちる)ようになりますので、特にフライパンの外側に頑固な油汚れが蓄積している場合にはおすすめです。
対して化学的リセット方法は「油汚れに対してはアルカリ性洗剤」「鉄の表面を溶かして根こそぎ落とすためには酸性洗剤」を利用します。日常的な汚れ落としにはアルカリ性洗剤を使い、物理的リセットはできないが根本的にリセットしたい場合には酸性洗剤を使います。
このことからも基本は物理的なリセット方法になります。
物理的なリセット方法について

物理的なリセット方法は高温に熱してリセットします。
油汚れや焦げ付き汚れを燃やして(炭化させて)落とすことになりますので、油膜は除去できるものの酸化皮膜は保たれることになります。リセット後に酸化皮膜を形成させる必要がありませんので、酸性洗剤を使うよりも手軽にできます。
高温にできる設備が整っているのであればおすすめできる方法です。
カセットコンロやガスバーナーなどを利用して熱します。
step.1
油汚れが燃えて炭化していきます。
step.2
炭化した油汚れをパームたわしなどで落としていきます。
step.3
どうしても落ちない場合には金たわしや真ちゅうブラシなどを使います。
step.4
この方法で赤サビも落とせます。
赤サビ(Fe2O3)は鉄を侵食してダメにしてしまうサビです。赤サビは高温に熱することにより体積の減少により剥離しやすくなるという性質がありますので、焼いた後には軽くこするだけでも落とせます。
比較的軽度の赤サビであれば、やすりなどを使う必要はありません。
化学的なリセット方法について
化学的なリセット方法には洗剤を利用します。
このリセット方法には「重曹などのアルカリ剤を使って油膜を落とす方法」と「酸性洗剤を使って鉄の表面を溶かして落とす方法」の2種類があります。前者は日常的な手入れに役立つ方法で、後者は根本的にリセットしたい場合に役立つ方法です。
鉄フライパンの状態により使い分けます。
- アルカリ性洗剤:重曹(炭酸水素ナトリウム)、セスキ炭酸ソーダ(セスキ炭酸ナトリウム)、酸素系漂白剤など
- 酸性洗剤:クエン酸、トイレ用洗剤など
- 軽度の油汚れや焦げ付き

重曹ペースト(重曹:水=2:1)を使ってこすり落とします。(※スポンジではなく丸めたラップやアルミホイルなどを使うと研磨力が得られます)
style.1
- 中度の油汚れや焦げ付き

重曹もしくはセスキ炭酸ソーダ水(水1Lに対して大さじ4ほど)でしばらく煮てそのまま冷ましてからパームたわしなどでこすります。
style.2
- 重度の焦げ付きや赤サビ

酸性洗剤(スルファミン酸など)で湿布をしてから重曹ペーストなどでこすり落とします。ここでは「LION トイレのルック(スルファミン酸0.8%)」を使っています。
style.3
酸性洗剤はリセット方法における最終手段です。
重曹やセスキ炭酸ソーダはアルカリにより油汚れを落としていますが、酸性洗剤は鉄の表面を溶かすことにより落としています。目に見えて形状が変化することはありませんが、酸化皮膜(四酸化三鉄)まで除去されることになりますのでサビやすくなります。
また強すぎる酸性洗剤を使うとフライパンをダメにしてしまうこともあります。
リセット後のシーズニングについて
リセット後はほぼ新品の状態に戻ります。
そのまま放置してしまってはすぐにサビてしまいますし、シーズニングをせずに使い始めれば料理がくっついてしまってストレスになることがあります。このことからもリセットとシーズニングはセットで考える必要があります。
時間に余裕のある時に作業してください。
まとめ・鉄フライパンを再生(復活)させるには?
鉄フライパンは何度でもリセットできます。
使いづらくなってしまったり長年使わずにサビさせてしまった鉄フライパンであっても、リセットすることにより新品に近い状態まで再生させることができます。シーズニング(油ならし)がうまくいかなかった場合にも何度でもやり直せます。
鉄フライパンを扱う上では覚えておきたいテクニックのひとつになります。
おすすめの関連アイテム
厚板フライパン 極(リバーライト)
- 材質:
- 鉄(特殊熱処理)
- 板厚:
- 3.2mm
- 重量:
- 0.83kg
リバーライトの厚板タイプです。
特殊熱処理(窒化処理)が施されていることに加え「3.2mmの厚板仕様になっている(通常タイプは1.6mm)」「木製のハンドルが採用されている」などの特徴があります。これにより「耐摩耗性や耐食性に優れる」「酸化皮膜を形成させる必要がない」「熱容量が高いことにより料理の仕上がりが良くなる」「ハンドルが熱くならない」などのメリットが得られます。
管理人のレビュー
特殊熱加工が施されていることに加え「一般家庭の台所においても違和感のないデザイン」が気になっています。現在使用している鉄フライパンはデバイヤーですが、機会があれば使いたい(切り替えたい)と考えています。
IH対応鉄フライパン(デバイヤー)
- 材質:
- 鉄
- 板厚:
- 2.5mm
- 重量:
- 1.38kg
デバイヤーの定番鉄フライパンです。
盛り付けをしやすいハンドル角度とデザインの良さが魅力の鉄フライパンです。高品質な厚板の鉄が使われていることもあり、安価な鉄フライパンと比べると格段に使いやすい(食材がくっつきにくくサビにくい)仕様になっています。
管理人のレビュー
デザインの良さが気に入って使っています。しかしデバイヤーの特徴ともいえるハンドル角度には「蓋が干渉してしまう」というデメリットもあります。お使いの蓋の流用を考えている場合には注意が必要です。
打出し 鉄 フライパン(山田工業所)
- 材質:
- 鉄(打ち出し)
- 板厚:
- 2.3mm
- 重量:
- 1.25kg
山田工業所の定番フライパンです。
通常の鉄フライパンはプレス(圧力を加えて成型する方法)などで作られていますが、山田工業所の鉄フライパンは打ち出し(たたいて成形する方法)で作られています。これにより鉄の分子が詰まり、硬く粘りのある性質を持つようになります。
管理人のレビュー
機能性を重視するのであれば山田工業所の打出し鉄フライパン一択かと思います。事実、多くの飲食店では山田工業所の鉄フライパンや中華鍋が好まれています。デザインが好みで台所の印象と合うのであれば心からおすすめできます。
竹ささら(遠藤商事)
- 材質:
- 竹
- 長さ:
- 235mm
- 重量:
- 105g
中華鍋に用いられることの多い竹ブラシです。
家庭での鉄フライパンの洗浄には少し長めに感じられるかもしれませんが、熱を持ったまま洗うことの多い鉄フライパンの洗浄では少し長めくらいの方が使いやすいです。気兼ねなく使える価格帯であることからもおすすめできます。
管理人のレビュー
一般的な竹ささらです。そのままでは硬く洗いにくいことからも「10分ほど煮る」「束ねられている部分に瞬間接着剤をしみ込ませる」「先端を剪定鋏などで斜めにカットする」などをして扱いやすくすることをおすすめします。
フライパン洗い ブラシ(マーナ)
- 材質:
- 馬毛
- 長さ:
- 25cm
- 重量:
- 80g
柔らかい馬毛のブラシです。
馬毛は耐熱・耐薬品性に優れているため、表面を傷つけることなく優しく洗い上げることができます。鉄フライパンを洗うには心もとなく感じられるかもしれませんが、ある程度育っているフライパンに洗剤を付けて洗う場合にはおすすめできます。
管理人のレビュー
鉄フライパンの扱いに慣れていない場合には竹ささらをおすすめします。しかしほとんど焦げ付かせることがなく育ってきた油膜を傷つけないように洗いたい場合などには重宝します。ある程度の油慣れをしているフライパンであれば洗剤で洗っても問題ありません。
超強力マグネットフック(Sendida)
- 材質:
- ステンレス鋼
- 耐荷重(垂直方向):
- 10kg
- 耐荷重(水平方向):
- 7kg
強力なマグネットフックです。
フック部分の回転する強力マグネットフックですので、溝やつなぎ目の少ないタイプのレンジフードでも鉄フライパンなどを吊るす(かける)ことができます。耐荷重は「垂直方向10kg」「水平方向7kg」ですので厚板の鉄フライパンであっても安心です。
管理人のレビュー
レンジフードには溝のあるタイプ(ブーツ型)と溝のないタイプ(スリム型)の2種類があります。ブーツ型の場合は溝に掛けるタイプのフックを使えますが、スリム型の場合には超強力なマグネットタイプのフックがおすすめです。