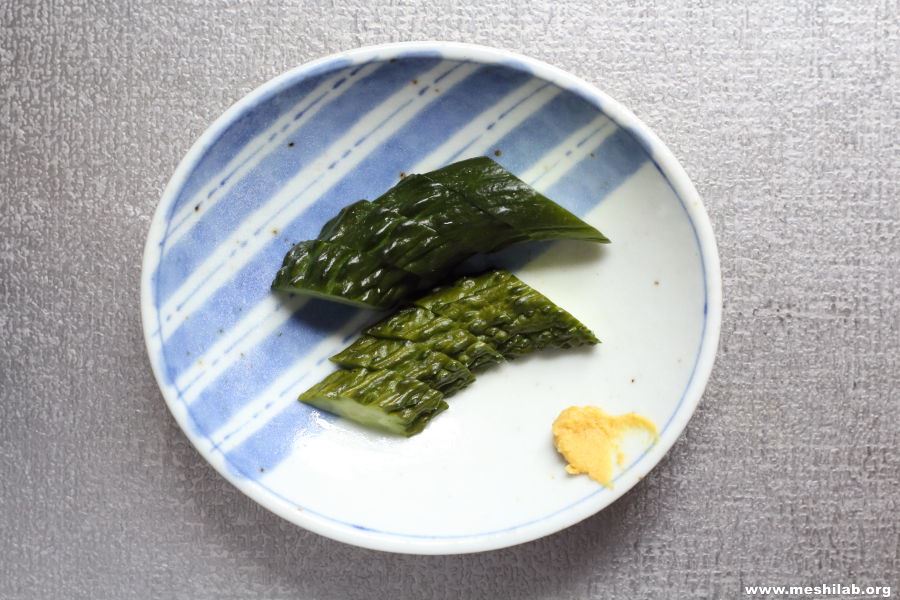この記事は約 4 分で読めます。
こんにちは、めしラボです。
一言にみそといっても、イメージされるみそは人それぞれです。東北地方にお住まいであれば米みそ(赤色辛みそ)をイメージされる方が多いはずですし、九州地方にお住まいであれば麦みそをイメージされる方が多いはずです。
みそには材料や熟成期間によって様々な種類があります。
 めしラボ
めしラボ今回の記事は次のような人におすすめ!
- みそにはどのような種類があるのか?
- みその種類による材料や熟成期間の違いは?
- みその種類による塩分濃度の違いは?
みそには複数の種類があります。
たとえば材料による分類では「米みそ、麦みそ、豆みそ」などに分けられ、熟成期間による分類では「白みそ、赤みそ(淡色みそ、赤色みそ)」などに分けられます。また塩分濃度の違いによる「甘みそ、辛みそ」などの分類方法もあります。
さらには分解型みそと発酵型みそという分類もあります。
スポンサーリンク
みその材料による種類分けとは?
みそは原料の違いにより大きく3種類に分けられます。
それが米麹を使って仕込まれる米みそ、麦麹を使って仕込まれる麦みそ、豆麹を使って仕込まれる豆みその3種類です。分量や仕込み方には多少の地域差はあるものの、基本的には蒸した大豆に塩と麹(米麹、麦麹、豆麹)を混ぜ込んで作られています。
みそ作りは意外とシンプルです。
- 米みそ:大豆、米麹、食塩
- 麦みそ:大豆、麦麹、食塩
- 豆みそ:大豆、豆麹、食塩 (※豆麹と食塩だけの場合もあり)
好まれるみそには地域差があります。
全国的には米みそが一般的ではありますが、九州地方では麦みそ、東海地方では豆みそが好まれる傾向にあります。また関東以北では米みそ単体、関東以西では調合みそ(米と麦を合わせたみそ)が好まれる傾向もあります。
加えて同じ種類のみそであっても材料の配合割合には地域差があります。
みその熟成期間による種類分けとは?
みその色の濃淡は熟成期間に起因しています。
みその色には大きく白みそと赤みそ(淡色みそ、赤色みそ)があります。これらのみその色味が異なるのは熟成によりメイラード反応(糖分とアミノ酸が反応して起こる褐変反応)が進むことでメラノイジンが生成されているためです。
メイラード反応は着色、香気成分の生成、抗酸化成分の生成などに関与しています。
- 白みそ(分解型みそ):麴由来の酵素による分解反応
- 赤みそ(発酵型みそ):酵素、乳酸菌、酵母などによる分解反応
白みそと赤みその熟成期間は大きく異なります。
白みそ(分解型みそ)は米麹の割合を高くしたうえで食塩の割合を低くすることにより短期間(2週間ほど)で完成させますが、赤みそ(熟成型みそ)は米麹の割合が低いうえに食塩の割合が高いことからも時間(冬に仕込んだ場合にはひと夏を越させるほどの期間)を要することになります。
この違いがメイラード反応の違いとなり色味の違いとなって現れます。
みその塩分濃度による種類分けとは?
みそには種類によるおおよその塩分濃度があります。
厳密なルールがあるわけではありませんが甘みそであれば7~12%、辛みそであれば11~13%に調整されています。これにより甘みそは短期間で甘みのあるみそになりますし、辛みそは長期熟成に耐えられてコクのあるみそになります。
以下は食品成分表からの一部引用です。
| 塩分濃度 | |
|---|---|
| 米みそ | 甘みそ:6.1% 淡色辛みそ:12.4% 赤色辛みそ:13.0% |
| 麦みそ | 10.7% |
| 豆みそ | 10.9% |
甘みそを長期熟成させることはできません。
みそを長期熟成させるためには「みそに含まれる水分に対する食塩濃度(対水食塩濃度)を19%以上」にする必要があります。対水食塩濃度を19%以上にすることによって雑菌の増殖を防いで耐塩性を有する酵母や乳酸菌などの有益菌がゆっくり仕事をできる環境を作り出すことができます。
このことからも、基本的には「甘みそ=分解型みそ」「辛みそ=発酵型みそ」になるのがセオリーとなっています。
まとめ・みその種類は?
みその分類方法にはいくつかの種類があります。
たとえば原料による分類には「米みそ、麦みそ、豆みそ」などがあり、熟成期間による分類には「白みそ、赤みそ(淡色みそ、赤色みそ)」など、塩分濃度による分類には「甘みそ、辛みそ」などがあります。また分解型みそと発酵型みそという分類方法もあります。
一見複雑そうに感じられるかもしれませんが、理屈を理解できていれば混乱することはなくなるはずです。