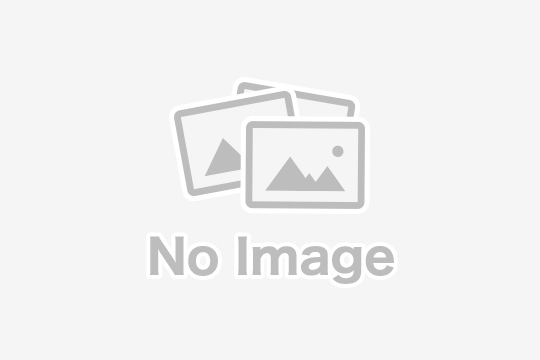この記事は約 5 分で読めます。
こんにちは、めしラボです。
鉄フライパン愛好家の中では「フライパンが育つ」と表現することがあります。これはフライパンを使い続けることで、油脂が重合することにより形成される油膜が強固になっていくためです。そのため鉄フライパンは使い続けることで使いやすくなります。
また使い手が育つことも使いやすくなっていく要因になっています。
 めしラボ
めしラボ今回の記事は次のような人におすすめ!
- 鉄フライパンが育つとはどのような状態か?
- 育てるためにやってはいけないことは?
- 使い手が育つとはどのような意味か?
調理は道具と使い手を育てます。
鉄フライパンは使い込まれることで育っていきます。しかし一定レベルを超えるとそれ以降は油膜ではなく使い手の問題になりますので、数週間も使われていれば使い込まれたフライパンと同等の扱いやすさになることもあります。
5年、10年という使用期間に特別なメリットはありません。
スポンサーリンク
鉄フライパンが育つことの意味は?
鉄フライパンが育つことは油膜が育つことです。
フッ素樹脂加工のフライパンに食材がくっつかないのは、食材がくっつく要因が「筋形質タンパク質の球状タンパク質が熱凝固する過程で一時的に活性基を露出させ、露出しているタイミングで金属面に触れていると金属と結びついてしまう」ためです。
そのため油膜により食材が直接金属に触れないようにします。
鉄フライパンの油膜は油脂が重合することにより形成された樹脂層(ポリマー層)ですので、油脂を劣化させるほどに油膜は強固になっていくということになります。
| 酸化促進因子 | 仕組み |
|---|---|
| 酸素 | 自動酸化の直接原因物質 |
| 光 | ラジカル生成により酸化が速まる |
| 温度 | 温度が高いと酸化速度が速くなる |
| 促進触媒 | 自動酸化に触媒的に作用する |
くず野菜を炒めることがあるのは油脂を劣化させやすいためです。
油脂の劣化は「酸素、光、温度、促進触媒」により促進されますが、炒め物には光以外の促進因子がすべて含まれていますので劣化(油脂の重合)が進みます。新しい鉄フライパンやスキレットには香味野菜を炒めると良いいうのも本質的には油脂の劣化を狙ってのことです。
また鉄フライパンの育ちやすさには油脂の種類も関連しています。たとえば不乾性油に分類されているオリーブオイルは油膜の育ちにくい油に分類されていますが、半乾性油に分類されている菜種油や大豆油は油膜の育ちやすい油に分類されます。
日常使いの油には、炒め物向きで比較的ヨウ素価の高いものを選ぶことがポイントです。
使い手が育つことの重要性とは?
鉄フライパンの使い方にはコツがあります。
フッ素樹脂加工(テフロン加工など)のフライパンと同じ使い方をしてしまえば高い確率で「食材がくっついてしまって調理にならない」「すぐにサビてしまって使い物にならない」などの問題が生じることになります。
特に注意して欲しいのが以下の3点です。
- 煙が出るまで空焼きをしてから油を引く
- 使用後の鉄フライパンは念入りに洗って乾かす
- 苦手な食材があることを理解する
鉄フライパンは200~250℃まで熱してから油を引きます。
これは鉄には化学的に結合している水分(吸着水)が付着しているためであり、吸着水の離れる200~250℃まで熱してから油をひかなければ油なじみが悪くなります。たったこれだけのことでも驚くほどに使いやすくなります。
次に使用後は念入りに洗うことです。
洗い残しがあると表面に電位差ができてしまって鉄が腐食します。これは鉄(Fe)がイオン化(Fe2+)して水酸化第一鉄(Fe(OH)2)となり、水酸化第一鉄はさらに酸化することにより水酸化第二鉄(2Fe(OH)3)や酸化第二鉄(Fe2O3)になるという反応です。
最後に苦手な食材があることを理解することです。
鉄は酸に反応する金属ですのでpH(水素イオン指数)の低いトマトが主役の料理やお酢を多く含む料理を苦手とします。また鉄フライパンの油膜は油脂の重合により作られていますのでコンニャクや海藻などのようなアルカリ性の食材も少しだけ苦手としています。
使い手が育つことには鉄フライパンが育つこと以上の効果があります。
約10年使い込んだ鉄フライパンについて
画像は約10年使っている鉄フライパンです。
同じ年数使い込んでいたとしても、油膜の状態は使い手により大きく変わります。私は「半乾性油を使ったシンプルなシーズニング方法」と「キャノーラ油やオリーブ油を使った調理」を好んでいることもあり光沢のないマッドな仕上がりになっています。
この状態でも目玉焼きは滑ります。
使い手によっては「光沢のある堅い油膜」や「炭化物を巻き込んだ凹凸のある油膜」であることもあります。前者は乾性油を使ったシーズニングをしているためであり、後者はリセットすることなく使い込んでいるためにそのような油膜になっています。
日常的な調理に1年ほど使っていると、自分なりのスタイルが見えてくるはずです。
まとめ・育った鉄フライパンの特徴は?
鉄フライパンは育つフライパンです。
鉄フライパンは使い続けることで油膜が強固になっていきます。油膜が強固になると食材と金属面が直接触れにくくなるためにフライパンが扱いやすくなります。また使い手が鉄フライパンの扱いに慣れていくことも重要な要素になっています。
しかし使い込むことによる鉄フライパン自体の成長は(正しく使えている場合には)数ヵ月間以降はさほど大きなものではありません。
おすすめの関連アイテム
厚板フライパン 極(リバーライト)
- 材質:
- 鉄(特殊熱処理)
- 板厚:
- 3.2mm
- 重量:
- 0.83kg
リバーライトの厚板タイプです。
特殊熱処理(窒化処理)が施されていることに加え「3.2mmの厚板仕様になっている(通常タイプは1.6mm)」「木製のハンドルが採用されている」などの特徴があります。これにより「耐摩耗性や耐食性に優れる」「酸化皮膜を形成させる必要がない」「熱容量が高いことにより料理の仕上がりが良くなる」「ハンドルが熱くならない」などのメリットが得られます。
管理人のレビュー
特殊熱加工が施されていることに加え「一般家庭の台所においても違和感のないデザイン」が気になっています。現在使用している鉄フライパンはデバイヤーですが、機会があれば使いたい(切り替えたい)と考えています。
IH対応鉄フライパン(デバイヤー)
- 材質:
- 鉄
- 板厚:
- 2.5mm
- 重量:
- 1.38kg
デバイヤーの定番鉄フライパンです。
盛り付けをしやすいハンドル角度とデザインの良さが魅力の鉄フライパンです。高品質な厚板の鉄が使われていることもあり、安価な鉄フライパンと比べると格段に使いやすい(食材がくっつきにくくサビにくい)仕様になっています。
管理人のレビュー
デザインの良さが気に入って使っています。しかしデバイヤーの特徴ともいえるハンドル角度には「蓋が干渉してしまう」というデメリットもあります。お使いの蓋の流用を考えている場合には注意が必要です。
打出し 鉄 フライパン(山田工業所)
- 材質:
- 鉄(打ち出し)
- 板厚:
- 2.3mm
- 重量:
- 1.25kg
山田工業所の定番フライパンです。
通常の鉄フライパンはプレス(圧力を加えて成型する方法)などで作られていますが、山田工業所の鉄フライパンは打ち出し(たたいて成形する方法)で作られています。これにより鉄の分子が詰まり、硬く粘りのある性質を持つようになります。
管理人のレビュー
機能性を重視するのであれば山田工業所の打出し鉄フライパン一択かと思います。事実、多くの飲食店では山田工業所の鉄フライパンや中華鍋が好まれています。デザインが好みで台所の印象と合うのであれば心からおすすめできます。
竹ささら(遠藤商事)
- 材質:
- 竹
- 長さ:
- 235mm
- 重量:
- 105g
中華鍋に用いられることの多い竹ブラシです。
家庭での鉄フライパンの洗浄には少し長めに感じられるかもしれませんが、熱を持ったまま洗うことの多い鉄フライパンの洗浄では少し長めくらいの方が使いやすいです。気兼ねなく使える価格帯であることからもおすすめできます。
管理人のレビュー
一般的な竹ささらです。そのままでは硬く洗いにくいことからも「10分ほど煮る」「束ねられている部分に瞬間接着剤をしみ込ませる」「先端を剪定鋏などで斜めにカットする」などをして扱いやすくすることをおすすめします。
フライパン洗い ブラシ(マーナ)
- 材質:
- 馬毛
- 長さ:
- 25cm
- 重量:
- 80g
柔らかい馬毛のブラシです。
馬毛は耐熱・耐薬品性に優れているため、表面を傷つけることなく優しく洗い上げることができます。鉄フライパンを洗うには心もとなく感じられるかもしれませんが、ある程度育っているフライパンに洗剤を付けて洗う場合にはおすすめできます。
管理人のレビュー
鉄フライパンの扱いに慣れていない場合には竹ささらをおすすめします。しかしほとんど焦げ付かせることがなく育ってきた油膜を傷つけないように洗いたい場合などには重宝します。ある程度の油慣れをしているフライパンであれば洗剤で洗っても問題ありません。
超強力マグネットフック(Sendida)
- 材質:
- ステンレス鋼
- 耐荷重(垂直方向):
- 10kg
- 耐荷重(水平方向):
- 7kg
強力なマグネットフックです。
フック部分の回転する強力マグネットフックですので、溝やつなぎ目の少ないタイプのレンジフードでも鉄フライパンなどを吊るす(かける)ことができます。耐荷重は「垂直方向10kg」「水平方向7kg」ですので厚板の鉄フライパンであっても安心です。
管理人のレビュー
レンジフードには溝のあるタイプ(ブーツ型)と溝のないタイプ(スリム型)の2種類があります。ブーツ型の場合は溝に掛けるタイプのフックを使えますが、スリム型の場合には超強力なマグネットタイプのフックがおすすめです。