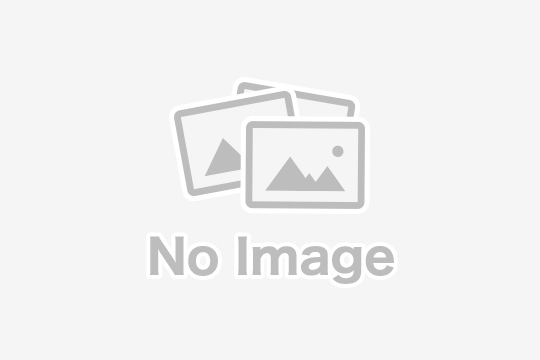この記事は約 4 分で読めます。
こんにちは、めしラボです。
ぬか床のレシピには「かつお節や煮干しなどを加える」ものがあります。しかしぬか床の管理に慣れていない(ぬか床の仕組みを理解できていない)のであればかつお節や煮干しなどを加えることはおすすめできません。
どうしても加えたい場合には少量から試してみることをおすすめします。
 めしラボ
めしラボ今回の記事は次のような人におすすめ!
- ぬか床からアンモニア臭が生じてしまう理由は?
- アンモニア臭の生じたぬか床が腐りやすくなる仕組みは?
- アンモニア臭を消すためにはどうすればいいのか?
ぬか床のアンモニア臭は危険サインです。
食材に含まれているたんぱく質は、微生物によってアミノ酸に分解されます。分解されたアミノ酸はアミノ基が離脱することでアンモニアになりますので、たんぱく質の過剰なぬか床からはアンモニア臭が生じてしまうことがあります。
ぬか床のアンモニア臭は、とても危険な状態です。
スポンサーリンク
アンモニア臭の原因は?
アンモニア臭の原因はたんぱく質です。
たんぱく質はアミノ酸に分解されることによりうま味となります。基本的にはぬか床を美味しくする成分です。しかし分解される過程でアンモニアが生じますので、たんぱく質の多すぎるぬか床はアンモニア臭くなってしまうことがあります。
このことからも、大豆(きな粉)などを加えたい場合には少しだけにします。
また、特に注意して欲しいのがかつお節や煮干しなどです。かつお節や煮干しの原料は海水魚です。海水魚には体液の濃度を維持するため(海水で脱水してしまわないため)に豊富なアミノ酸、アミン類、TMAO、尿素などが含まれています。
TMAO(トリメチルアミンオキシド)は分解されると「魚の腐ったような臭い」になりますし、尿素はアンモニアに変換されるために「アンモニア特有の刺激臭(掃除をしていないトイレのような臭い)」になります。
このことからも、ぬか床に加えるたんぱく質には注意が必要です。
アンモニア臭いぬか床は腐る?
アンモニアはぬか床を腐らせます。
ぬか床は6~8%の塩分濃度とpH4.3前後の水素イオン指数によって腐敗菌から守られています。しかしアンモニアはぬか床内の水分にOH–を増加させることでアルカリ性に替えますので腐敗菌の増えやすい環境になります。
たんぱく質を加えすぎたぬか床が腐りやすいのはアルカリ性になるためです。
たんぱく質食材を加えるとうま味が増す
アミノ酸が分解されてアンモニアが生じる
OH–が増加することでアルカリ性に傾く
アルカリ性に傾くことで腐敗菌が増えやすくなる
アンモニア臭のするぬか床の再生は困難です。
しかし不可能というわけでもありません。アルカリ性であるアンモニアは乳酸菌の産生する乳酸により中和されます。このことからも乳酸菌を増やすような手入れ(捨て漬け野菜を入れた上でかき混ぜる頻度を減らすなど)をすることによりアンモニア臭は和らいできます。
確実に再生できるとは限りませんが、試してみる価値はあります。
まとめ・ぬか床のアンモニア臭の原因は?
ぬか床がアンモニア臭くなってしまう原因には「たんぱく質を加えすぎてしまっている」「海水魚(かつお節や煮干しなど)を加えている」などがあります。
たんぱく質や尿素は分解されることでアルカリ性のアンモニアを増やしますので、酸性pHを好む乳酸菌や酵母が減ってアルカリ性を好む腐敗菌(大腸菌など)を増やしてしまいます。これらのことからも、アンモニア臭のするぬか床には早めの対処が必要です。
※ぬか床容器は価格変動が大きいため注意してください。常温管理には米ぬかをこぼしにくい寸胴型容器、冷蔵庫管理にはデッドスペースのできにくい角型容器がおすすめです。