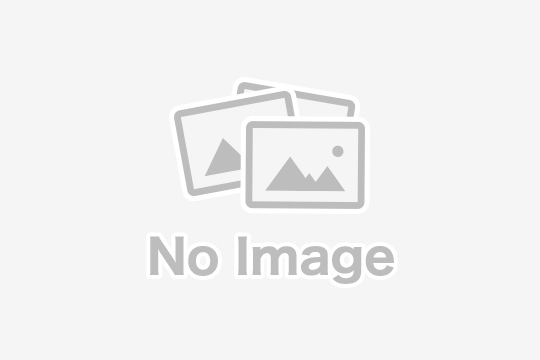この記事は約 6 分で読めます。
こんにちは、めしラボです。
購入したばかりの鉄フライパンは、そのまま使い始めることができません。新しい鉄フライパンには流通時のサビを防ぐために防錆塗装などが施されていますので、そのまま使い始めたのでは料理が台無しになってしまいます。
また鉄フライパンを使いやすくするための酸化皮膜や油膜を作ることもあります。
 めしラボ
めしラボ今回の記事は次のような人におすすめ!
- 鉄フライパンを使い始める前に最低限やるべきことは?
- 鉄フライパンをサビにくくするための一工夫とは?
- 鉄フライパンの種類によっては作業工程が違う?
新しい鉄フライパンは防錆塗装を落としてから使い始めます。
鉄フライパンに施されているサビ(自然酸化)を防ぐためのコーティングにはいくつかの種類があります。多くは焼き切ることのできるクリアラッカー塗装ですが、焼き切りにくい透明シリコン塗装のこともあれば、蜜蝋などのようにお湯で落とせることもあります。
これらのことからも取扱説明書の指示に従うのが基本になります。
スポンサーリンク
防錆塗装の落とし方について
新しい鉄フライパンには防錆コーティングが施されています。
防錆コーティングの種類にはメーカーや販売店による違いがありますので、基本的には取扱説明書の指示に従うことをおすすめします。多くは「クリアラッカー塗装」「透明シリコン焼付塗装」「蜜蝋や油など」の3パターンであるはずです。
特別な指示がない場合には「ラッカー塗装」の可能性が高いです。
- クリアラッカー塗装:空焼きにより焼き切るタイプ
- 透明シリコン焼付塗装:そのまま使い始めることのできるタイプ
- 蜜蝋や油など:お湯や洗剤で落とせるタイプ
特に注意して欲しいのがラッカー塗装です。
クリアラッカー塗装は加熱により強い刺激臭を発しますので、焼き切らずに使い始めてしまうと料理が台無しになってしまいますし、人体にも有害です。そのため確実に焼き切ってから使い始める必要があります。
少し面倒でも取扱説明書は隅々まで読んでください。
クリアラッカー塗装の除去方法
クリアラッカー塗装は焼き切ります。
多くの鉄フライパンはこのタイプになります。フライパンにラッカー塗料が吹き付けられていますので、直火に当てて空焼きすることにより塗料を焼き切ります。Siセンサーの付いているガスコンロでは焼き切れませんのでカセットコンロなどを使用します。
焼き切る過程で黒く刺激臭のある煙が出ますので注意が必要です。
煙が出なくなるまで空焼きすることがポイントになります。煙が出なくなれば粗熱が取れるのを待ってから洗剤で洗います。また(後で説明する)酸化皮膜を形成させる場合にはそのまま600℃付近まで加熱していきます。
600℃付近というのは鉄が鈍く赤くなりはじめる温度です。
透明シリコン塗装を除去しない理由
透明シリコン塗装は落とさずに使い始めます。
クリアラッカー塗装に次いで多いのが透明シリコン塗装です。人体には無害な透明シリコン塗装は、使用しているうちに徐々に剥がれ落ちていきます。そのため人為的に除去する必要はありませんので、そのまま使い始めることができます。
無理に剥がそうとしてもなかなか剥がれません。
酸化皮膜や油膜を形成するために透明シリコン塗装を除去したいと考えることもあるかと思いますが、鉄フライパンの黒色は高温に熱した鉄を延ばす工程で酸化して形成された黒サビ(四酸化三鉄)の色ですのでそのまま使い始めることをおすすめします。
銀色のフライパンの場合であっても無理に除去するメリットは大きくありません。
蜜蝋や油の除去方法
蜜蝋(または油など)はお湯や洗剤で落とします。
あまり多くはありませんが、蜜蝋や油でコーティングされていることもあります。これらのコーティングはお湯や洗剤で落とすことができますので焼き切る必要はありません。また油が塗られているだけではなくシーズニングが施されていることもあります。
シーズニングとは油膜(油脂を酸化させることで生じる樹脂皮膜)が形成されている状態ですので、軽く洗っただけでも使い始めることができます。鉄フライパンではあまり見かけませんが、ダッチオーブンやスキレットでは主流派となっています。
手軽に使い始めたい場合にはシーズニング済みの製品がおすすめです。
酸化皮膜の形成について
黒サビには赤サビを防ぎ油なじみも良くする効果があります。
サビ(酸化鉄)は鉄と酸素が化合してできる物質であり、自然には存在しない「酸化第一鉄(FeO)」、黒サビと呼ばれている「四酸化三鉄(Fe3O4)」、赤サビと呼ばれている「酸化第二鉄(Fe2O3)」の3種類があります。
注目すべきが黒サビと赤サビの違いです。
- 黒サビ(四酸化三鉄):鉄を安定させるサビ
- 赤サビ(酸化第二鉄):鉄を腐食させるサビ
黒サビには「赤錆を防ぐ」「油なじみを良くする」などの効果があります。
しかし黒サビを作るためには高温で熱する必要がありますので、作業が困難である場合には黒サビによる酸化皮膜を作らずに油膜を作ることもあります。ちなみに黒サビ(四酸化三鉄)の形成には585℃以上に熱する必要があります。
危険を伴うことからも必ずしも必要な作業ではありません。
樹脂皮膜(ポリマー層)の形成について
鉄フライパンは油膜により使いやすくなります。
料理が鉄フライパンにくっつくのは「筋形質タンパク質の球状タンパク質が熱凝固する過程で一時的に活性基を露出させ、活性基が露出しているタイミングで金属面に触れていることにより金属と結びついてしまう」でためす。
そのため油膜により金属面に直接触れないようにします。
油なじみの悪いフライパン
油切れを起こしやすい
活性基と金属面が接する
食材がくっついてしまう
タンパク質食材はくっつきやすいといえます。
油膜(樹脂皮膜)の形成には「油の種類」と「加熱方法」がポイントになります。鉄フライパンの油膜は油脂を重合させることで形成されますが、油脂の重合には「熱重合」と「酸化重合」があり、いずれの重合でも油脂の不飽和度が高いほどに重合速度が速いという特徴があるためです。
このことからも油膜は油脂の種類や加熱方法により異なる特徴を有することになります。くず野菜を炒めるだけでも形成されますが、より強固な油膜を作りたい場合には乾性油を薄く塗りのばした鉄フライパンをオーブンで焼く方法が選ばれます。
何度でもやり直せますので色々試してみることをおすすめします。
まとめ・新しい鉄フライパンを使い始めるには?
新しい鉄フライパンはそのままでは使い始められません。
まずは鉄フライパンに施されている防錆コーティングの種類を知ること、そしてラッカー塗料や蜜蝋などの場合には確実に落とすことがポイントになります。特にラッカー塗料を落とさずに使い始めてしまうと悲惨なことになります。
鉄フライパンの種類にもよりますが、最もシンプルな工程としては「防錆塗装を焼き切る→くず野菜を炒めて油膜を形成させる」ことにより使い始めることができるようになります。
おすすめの関連アイテム
厚板フライパン 極(リバーライト)
- 材質:
- 鉄(特殊熱処理)
- 板厚:
- 3.2mm
- 重量:
- 0.83kg
リバーライトの厚板タイプです。
特殊熱処理(窒化処理)が施されていることに加え「3.2mmの厚板仕様になっている(通常タイプは1.6mm)」「木製のハンドルが採用されている」などの特徴があります。これにより「耐摩耗性や耐食性に優れる」「酸化皮膜を形成させる必要がない」「熱容量が高いことにより料理の仕上がりが良くなる」「ハンドルが熱くならない」などのメリットが得られます。
管理人のレビュー
特殊熱加工が施されていることに加え「一般家庭の台所においても違和感のないデザイン」が気になっています。現在使用している鉄フライパンはデバイヤーですが、機会があれば使いたい(切り替えたい)と考えています。
IH対応鉄フライパン(デバイヤー)
- 材質:
- 鉄
- 板厚:
- 2.5mm
- 重量:
- 1.38kg
デバイヤーの定番鉄フライパンです。
盛り付けをしやすいハンドル角度とデザインの良さが魅力の鉄フライパンです。高品質な厚板の鉄が使われていることもあり、安価な鉄フライパンと比べると格段に使いやすい(食材がくっつきにくくサビにくい)仕様になっています。
管理人のレビュー
デザインの良さが気に入って使っています。しかしデバイヤーの特徴ともいえるハンドル角度には「蓋が干渉してしまう」というデメリットもあります。お使いの蓋の流用を考えている場合には注意が必要です。
打出し 鉄 フライパン(山田工業所)
- 材質:
- 鉄(打ち出し)
- 板厚:
- 2.3mm
- 重量:
- 1.25kg
山田工業所の定番フライパンです。
通常の鉄フライパンはプレス(圧力を加えて成型する方法)などで作られていますが、山田工業所の鉄フライパンは打ち出し(たたいて成形する方法)で作られています。これにより鉄の分子が詰まり、硬く粘りのある性質を持つようになります。
管理人のレビュー
機能性を重視するのであれば山田工業所の打出し鉄フライパン一択かと思います。事実、多くの飲食店では山田工業所の鉄フライパンや中華鍋が好まれています。デザインが好みで台所の印象と合うのであれば心からおすすめできます。
竹ささら(遠藤商事)
- 材質:
- 竹
- 長さ:
- 235mm
- 重量:
- 105g
中華鍋に用いられることの多い竹ブラシです。
家庭での鉄フライパンの洗浄には少し長めに感じられるかもしれませんが、熱を持ったまま洗うことの多い鉄フライパンの洗浄では少し長めくらいの方が使いやすいです。気兼ねなく使える価格帯であることからもおすすめできます。
管理人のレビュー
一般的な竹ささらです。そのままでは硬く洗いにくいことからも「10分ほど煮る」「束ねられている部分に瞬間接着剤をしみ込ませる」「先端を剪定鋏などで斜めにカットする」などをして扱いやすくすることをおすすめします。
フライパン洗い ブラシ(マーナ)
- 材質:
- 馬毛
- 長さ:
- 25cm
- 重量:
- 80g
柔らかい馬毛のブラシです。
馬毛は耐熱・耐薬品性に優れているため、表面を傷つけることなく優しく洗い上げることができます。鉄フライパンを洗うには心もとなく感じられるかもしれませんが、ある程度育っているフライパンに洗剤を付けて洗う場合にはおすすめできます。
管理人のレビュー
鉄フライパンの扱いに慣れていない場合には竹ささらをおすすめします。しかしほとんど焦げ付かせることがなく育ってきた油膜を傷つけないように洗いたい場合などには重宝します。ある程度の油慣れをしているフライパンであれば洗剤で洗っても問題ありません。
超強力マグネットフック(Sendida)
- 材質:
- ステンレス鋼
- 耐荷重(垂直方向):
- 10kg
- 耐荷重(水平方向):
- 7kg
強力なマグネットフックです。
フック部分の回転する強力マグネットフックですので、溝やつなぎ目の少ないタイプのレンジフードでも鉄フライパンなどを吊るす(かける)ことができます。耐荷重は「垂直方向10kg」「水平方向7kg」ですので厚板の鉄フライパンであっても安心です。
管理人のレビュー
レンジフードには溝のあるタイプ(ブーツ型)と溝のないタイプ(スリム型)の2種類があります。ブーツ型の場合は溝に掛けるタイプのフックを使えますが、スリム型の場合には超強力なマグネットタイプのフックがおすすめです。